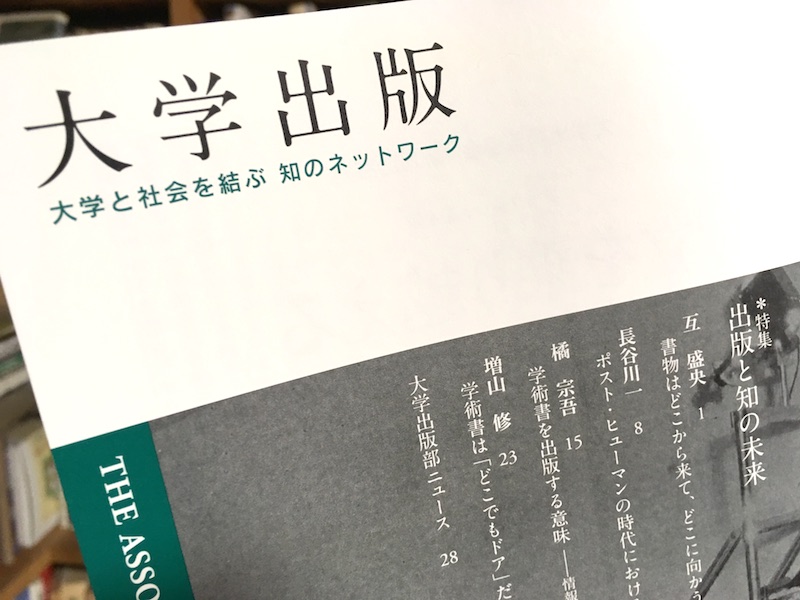日系アメリカ人ミキ・デザキが監督した初めてのドキュメンタリー映画『主戦場』をひじょうにおもしろく観た。必見の作品だとおもう。必見というのは、慰安婦問題という主題や内容についてもそうなのだが、それ以外にもいくつか重要な点があると考えるためだ。
第一は、この作品が全体として、監督自身がこのイシューをとらえ理解を深めてゆくためのプロセスになっている点である。
「ドキュメンタリー」を自称する作品は多い。だが、つくり手の考えが「答え」としてあらかじめあり、そこに向けて観客を説得してゆく場として作品がつくられているというケースが少なくない。それは、つくり手が、みずからのイデオロギーでもって観客を教化してゆこうとする「上から目線」の姿勢である。こういうタイプの姿勢は、ある時期までは映画でもテレビのドキュメンタリー番組でも支配的だった。いまでも、けっこうよく見かける。
この映画は、そうではない。監督自身が慰安婦問題について「知らない」「わからない」というところから始まり、作品をとおして監督がどんどんと理解を深めてゆく。そのプロセスがひじょうにスリリングだ。
たとえばマイケル・ムーアなどもやはり「知らない」という地点から始めるように見えるわけだが、かれのばあいの「知らない」はあくまで「ポーズ」であり、作品構成上の仕掛けでしかない。実際にはムーア自身の強固な世界像と明快すぎるほどの見解があり、その強烈な主体の下に作品が統合されているという点では、いたって古典的である。そうしたムーアの姿勢と照らし合わせたとき、本作品は現代性は際立っている。監督はもともとYouTuberから出発しているというから、本作品にはデジタルメディア世代の良質な部分が開花しているといってもいい。
第二は、作品を「仮想討論場」とする構成がすばらしい点である。とくに中盤までは、右派・左派が交互に登場して(引用も含めて)自説を開陳してゆくのだが、それは現実には実現することがまずありえない、慰安婦問題をめぐる討論の場となっている。監督は(高名なドキュメンタリー作家がときに示すように)その討論を高見からながめるのではなく、討議と同じ地平にいて観察している。そしてその監督の態度までも含めて、ぼくたち観客がその討議場をメタレベルから観察する。そんな入れ子式になった映画=観客の構造が実現されている。これもまた、ドキュメンタリー映像のきわめて重要な活用の仕方だとおもう。
ぼくはこの作品を試写で観た(公平を期すためにも記しておく)。当日の配布資料の中に,「映画は論文ではない」と述べておられる森達也さんの文章があった。つくり手の主観が大事だという趣旨とおもう。かれの言いたいことはよくわかるのだが、人文社会科学系のばあい(分野にもよるかもしれないが)事実の記述だけで論文ができあがるわけではない。再構成するためにはパースペクティヴが不可欠である。その点において、ぼくは『主戦場』を観ながら、よくできた社会学の論文に通じるものがあるように感じていた。
この映画の鑑賞経験の醍醐味は、監督がこうしたプロセスをとおして何段階か深い理解に到達してゆくさまを見る経験であるとおもう。
終盤部になると監督は、右派の主張の土台に巣くう問題を明らかにしつつ、ひとつの結論へと達しようとする。それは説得的ではあるものの、先を急ぐあまり、やや不十分で危なかしいところが見られないではない。「慰安婦問題」と「慰安婦像問題」を同じひとつのイシューととらえているようだが、両者は少し次元が異なるため区別したほうがいいのではないかと、個人的にはおもう。また、どちらの陣営もなぜアメリカ世論を「主戦場」としたがるのかについても、もっと掘り下げられているとよかった。
とはいえ、もちろん誰のどのような理解であれ、完全無欠な理解というものはありえない。不十分な点も含めてチャーミングな作品だというべきだろう。
主題からして、いまの日本の状況のなかでの上映には、いろいろむずかしい要素があるかもしれない。しかし、そうであればこそ、政治的立場にかかわらず、ひとりでも多くの方に観てもらえるとよい作品だとおもう。
東京ではイメージ・フォーラムにて4月20日から公開とのこと。
公式サイト:

予告編:
*若干の加筆修正、および写真を追加(190324)。